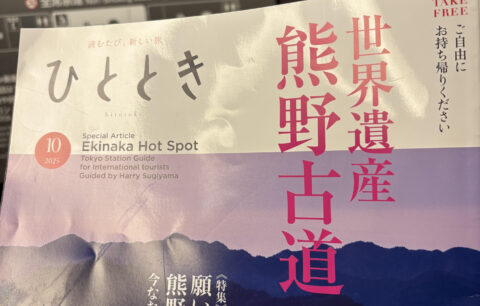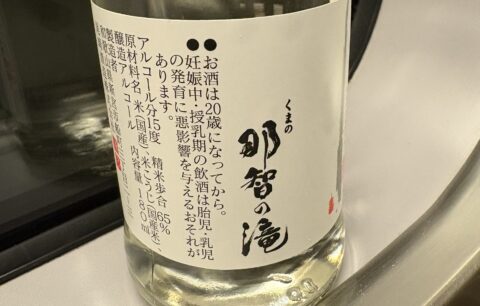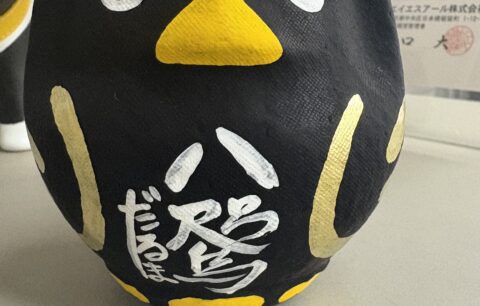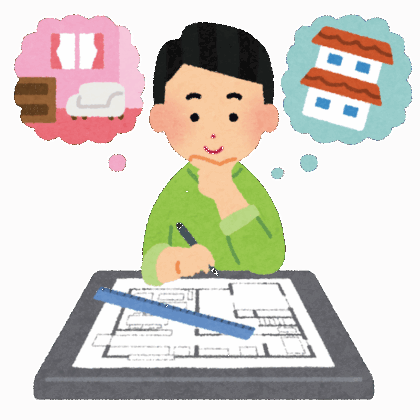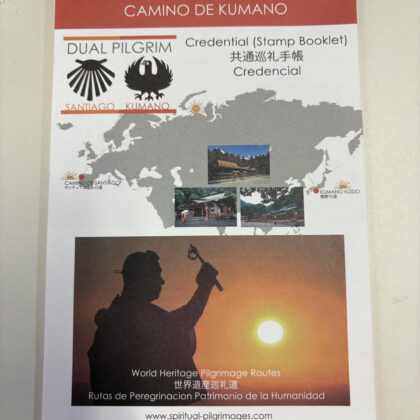例えば今の令和の天皇様が、34回も同じところにおまいりしてたら「一体なになに?」と思うのが通常だと思うのですが、まあそれくらいだったのがこの熊野詣・熊野御幸だったわけです。
日本サッカー協会の森保監督とか宮本キャプテンとかが、4年に1回五輪前に熊野詣するのもまたすごいことだとは思うのですが、それ以上にすごかったわけです。
歴代で言えば
・後白河法皇が34回、
・後鳥羽法皇が28回、
・鳥羽上皇が24回、
・白川上皇が12回、
花山法皇は1回、というより、出家させられて天皇やめさせられて泣く泣く那智に来て千日修行してたので、1回にも意味が違う気もしますが1回です。
中世・宇多上皇(第59代天皇)の延喜七年(西暦907年)から 玄輝門院の嘉元元年(西暦1303年)までの369年間に 上皇女院親王を合せて御23方、104回に及ぶ皇室の御参詣があり、これを熊野御幸と言って熊野三山史上に不滅の光彩を放っている。
熊野御幸には陰陽師に日時を占定させて、斉館で心身の御精進を数日向行われて後に御出発になる。白河天皇の天・永元年九月の御幸には、総人数八百十人 一日の食糧十六 石二斗八傅馬百匹と「中右記」に記している。
御幸の道順は京都・住吉・和泉・紀伊半島海岸沿いに南下して田辺・中辺路本宮熊野川を下って当大社へ 参拝・那智山雲取本宮、往路コースを逆行して帰京されるまでおよそ二枚日に及ぶ難行苦行の旅であった。
熊野御幸によって熊野信仰は公卿武士、庶民の間に 流布し、熊野水軍をもつ熊野三山の忠誠心を助長し、京と 熊野との文化交流有名な熊野懐紙、幾多の名歌が詠じら れるなど各方面に大きな影響を残している。